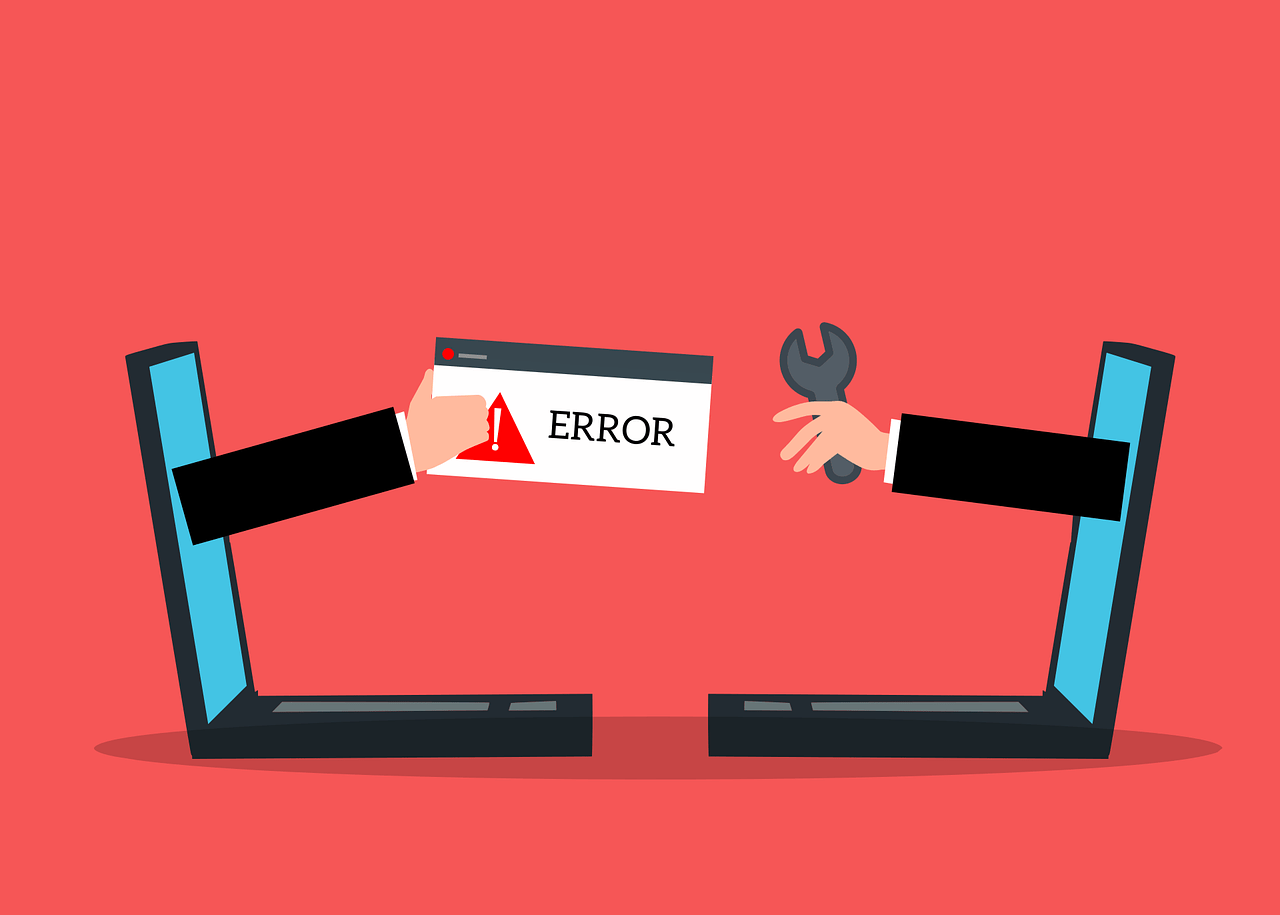去年令和6年分の所得が確定したあと、その内容をもとに住民税の計算が行われて令和7年5月以降住民税決定通知が会社などから受け取られているかと思います。
しかし、税額の変更などがあると住民税の変更通知が届く場合があります。
これが届いた場合には所得税の変更も忘れないようにしましょう。
住民税が変更される場合
住民税が変更される理由として多いのは、会社から提出された課税資料(給与支払報告書)で調査した結果住民税が変更になる、というものです。
- 配偶者控除を受けているのに妻の収入が多く配偶者控除が受けられないことがわかった
- 配偶者控除を受けているのに妻の収入が多く配偶者特別控除へと変更になった
- 扶養控除を受けているのに子どもの収入が多く扶養控除が受けられないことが分かった
などが多いです。
例えば、Aに勤務する従業員の息子(大学生)がアルバイト先Bの収入が扶養控除の要件である所得48万円を超えているにもかかわらず扶養控除を受けていたとします。
従業員の給与支払報告書がAからお住まいの市区町村に届き、息子が働くBの勤務先の給与支払報告書も届きます。
AとBの給与支払報告書の内容を照らし合わせて税額に誤りがあったら住民税の再計算をして変更通知が作成されます。
そして従業員の勤務先であるAに住民税変更通知が届き今後修正した住民税を納めていく形になります。
所得税も変更をする
Aに届いた住民税変更通知書の内容とすでに提出している給与支払報告書(源泉徴収票)と見比べてみましょう。
どこが違っているでしょうか。
今回の例ですと、扶養控除の金額が0円に変更になっていると思います。
では、住民税だけ変更すれば終わりかというとそうではありません。
扶養控除が誤っているということは所得税を計算する際にも扶養控除を入れて計算してしまっていますよね。
なので、所得税も扶養控除を0円に変更して再計算をしないといけません。
その計算をする義務があるのは、源泉徴収をする義務のある従業員の勤務先Aです。
Aでは給与について年末調整を行い、源泉徴収票を作成してその内容を給与支払報告書として市区町村へ提出しています。
そのため、Aでは扶養控除を変更したうえで再度年末調整をやり直す必要があります。
結果、当初の税額よりも多く税額が計算されますので、その差額分をAを通じて税務署へ納付することになります。
したがって、その従業員から納付する分を徴収する必要がありますので、従業員とその息子に徴収する理由をしっかり説明しなければなりません。
この税務署への納付をAが行うことを「扶養是正」と言ったりします。
扶養是正は「扶養控除等の見直し」という文書で税務署から10月前後に郵送されてきますので届いてから年末調整の再計算をして納付するという形が多いですね。
令和6年分の扶養是正の注意点
実は、扶養是正に関しては令和6年分は大きな注意点があります。
それは、昨年定額減税が行われたことによる影響があるからです。
たった1年のこの制度により、扶養控除等に誤りがあった場合定額減税の対象にならなくなる人が出てきてしまうのです。
例えば、従業員と妻(同一生計配偶者)と息子(大学生・扶養親族)の3人家族ですと、定額減税額は30,000円×3人=90,000円です。
①本人
②同一生計配偶者:生計を一にする配偶者で所得48万円以下の人
③扶養親族:生計を一にする親族で所得48万円以下の人
扶養親族である息子は扶養控除を受けていますが、アルバイト収入が多くて所得48万円を超えてしまっていました。
その場合、所得48万円を超えてしまっているので③の扶養親族には当たらないことになりますので、30,000円×2人=60,000円へと定額減税額が減ることになります。
したがって、令和6年分に関しては2つの修正が必要になります。
- 扶養控除(大学生なので特定扶養親族)63万円→0円の修正
- 定額減税額9万円→6万円の修正
また、例えば、配偶者が所得48万円を超えている場合、配偶者控除から配偶者特別控除へと変更になりますが所得95万円までは控除額38万円で変わりません。
しかし、定額減税の対象者②の同一生計配偶者にはあたりませんので、定額減税額は1人少ない金額で修正をしなければなりません。
まとめ
住民税変更通知が来た場合の対応と注意点をまとめてみます。
- 住民税の変更理由を確認する
- 所得税もあわせて修正が必要
- 勤務先が所得税の修正を行う
- 令和6年分は「定額減税」も修正対象となる
住民税変更通知が来たら所得税も修正しないといけないというのは押さえておきたいところです。
さらに、令和6年分に関しては定額減税が絡んでおりそれも踏まえて所得税を修正しなければならないためかなりめんどくさくなります。
今後混乱しそうな気配がします。
では。