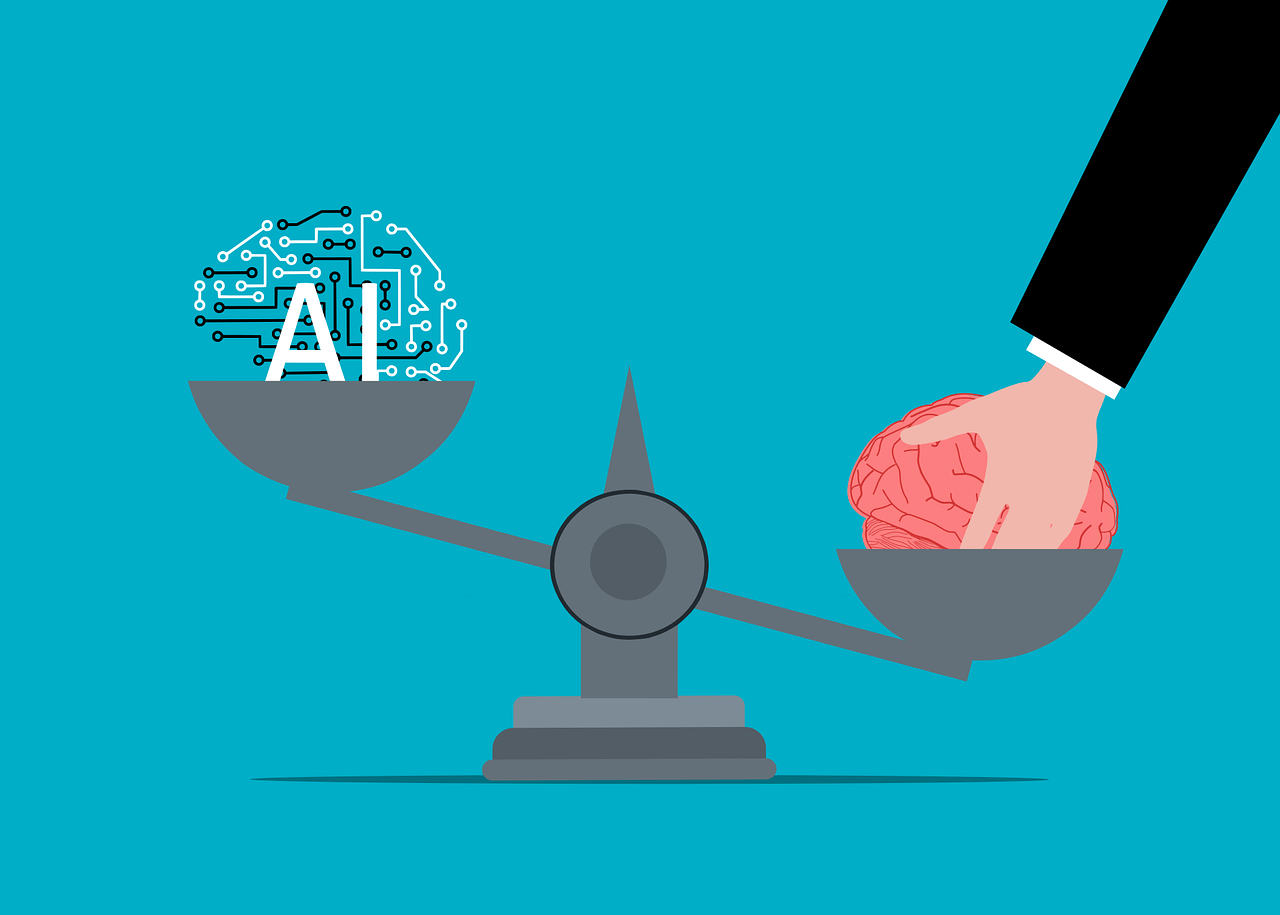今税理士・社労士業をしていて生成AIを使う場面が増えてきています。
しかし、私はそれに完全に頼り切っているかというとそうでもありません。
何を使うのかを事前に決めています。
生成AIができることが広がっている
生成AIでできることはかなり広がっています。
テキスト・画像・音声・音楽・動画などをAIに指示すれば生成してくれます。
作業を効率化することだったり新たなアイデアやヒントを提供したり、自分好みにアレンジを加えることもできます。
しかし、一方でAIが指示を理解できず誤った情報を生成したりプライバシーやセキュリティの問題も取り出されています。
よくChatGPTを使って会話をしている、というニュースを見かけることがあります。
暇つぶしにはなるかもしれませんけど指示があいまいなままなら求めている回答が得られない可能性があります。
年金相談を受ける前にAIで調べてきたというお客様が最近多いのですが、間違った情報をあたかも正しいと思い込んで混乱されるケースを目にするようになりました。
【事務所お知らせ】生成AIを利用している場面
私も生成AIはよく利用しています。
- パワポ資料の作成
- 税金や年金の試算
- 文章の校正
- 要約
が主な使い方です。
パワポ資料の作成
研修講師を担当させていただくときや、記帳指導・スポット相談で説明をさせていただくときにパワポで資料を作成しお渡ししています。
もともと図を入れたりするのが苦手なんですけど文章ばかりのものを見てもきっとわかりづらいなと自分でも感じることがありました。
そこで生成AIに作成した文章を読み込ませて「まとめの図」を生成してもらい挿入したりしています。
Napkinはよく使いますね。
Gensparkですと文章を読み込ませるだけでパワポ資料が出来上がりますが、かなり指示を出さないと希望のものにはなりませんので有料がおススメです。
税金や保険料の試算
税金や年金額を試算できるアプリを生成AIで作っています。
例えば、個人事業主の所得税・住民税・事業税・国民健康保険を試算できるようにしています。
収入や所得・所得控除・世帯人数や年齢を入れると自動で計算できます。
プログラミングの専門知識は私はないのですが生成AIに指示を出してプログラミングコードを生成してもらいます。
ただこちらも1回の指示ですべて完璧になるわけではなく試行錯誤してようやくできあがります。
同業者の税理士がブログなどで書かれているのを拝見しながらやってみています。
文章の校正
ブログやメルマガを書いていると誤字脱字が気になることがあります。
また、メール文章を考えてもらったり依頼文を校正してもらうために使っています。
要約
国税庁ホームページにアップされる資料や日本年金機構にアップされる資料を読み込ませて要約をしてもらいます。
膨大な資料になることもありますので、要約した内容をもとに読み始めたほうが理解は進むような気がしています。
12月になると来年度の税制改正大綱が公表されますのでそちらも生成AIで読み込ませています。
それ以外のことは使わない
実は、以上の4つの場面しか生成AIは使っていません。
…というかほかに使っていたことはあるのですが、時間がかかるわりに効率化が図れなかったのです。
結局、今生成AIを使う場面は仕事がメイン。
生成AIよりもこれまでやってきたことをレベルアップしたほうが効率的なのではないかと。
例えば、ExcelやRPAを学ぶとかですね。
あと自分が期待するものを生成しようとすると指示を何度も出さないといけませんし、結局その生成したことが実は間違っていたという危険性もあるのです。
そのため、生成AIの利用範囲は決めておいたほうがいいと私は思います。
まとめ
今日は私が生成AIを利用している場面について書いてみました。
意外と使いこなせていない気がしますけど、今の仕事を考えるとこれ以上のことは求めていません。
ただその都度必要なことが思い浮かんだら生成AIを使えるかどうかを考えるくらいでいいのではないかなと思います。
では。