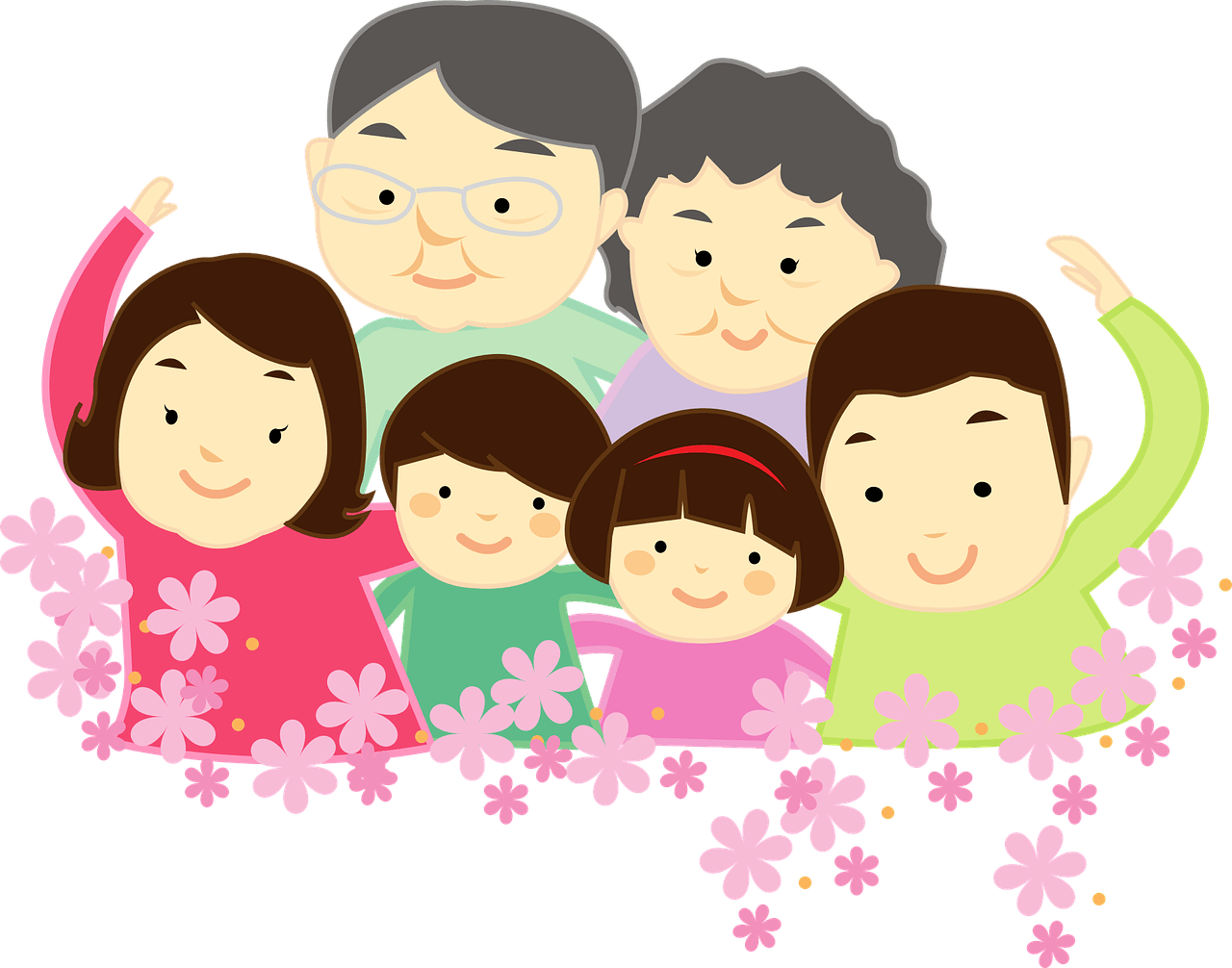税金と社会保険で扶養に入る・入らないは取り扱いが異なっています。
なんで取り扱いを一緒にしないのかな?というのはずっと疑問に思っています。
ポイントは「収入と所得」
今回は夫婦のうち、妻を夫の扶養に入れるという例を考えてみます。
夫はサラリーマンで、妻はパート勤務をしています。
扶養に入るメリットは、
- 税金面:配偶者控除が受けられる
- 社会保険
①健康保険・年金保険料:妻の保険料はかからない
②年金:妻は国民年金を納付したものとされるため年金がもらえる
一般的に扶養に入るメリットで注目されるのは社会保険かなと。
では、扶養に入るか入らないかの判断基準を考えてみます。
税金は妻が所得48万円以下なら配偶者控除を受けることができます。(令和7年12月からは所得58万円以下になります)
社会保険は、60歳未満の妻なら収入130万円未満(60歳以上は収入180万円未満)が扶養に入るひとつの基準となっています。
税金は所得・社会保険は収入でみるという違いがあります。
【事務所お知らせ】収入と所得の違い
妻はパート勤務をしていますので、給与をもらいます。
給与収入とは所得税などを差し引かれる前で手取り額ではありません。
給与収入から経費に相当する給与所得控除を差し引いたものが所得(もうけ)となります。
例えば、パート収入が100万円である妻の場合は、給与所得控除は最低額の55万円と決まっていますので所得は45万円となります。
45万円の所得であれば所得48万以下になりますので、税金の配偶者控除を夫は受けることができます。
社会保険の収入は範囲が広い
次に社会保険の収入についてですけど、妻は55歳でパート収入のほか前職を退職してから失業給付をもらっていた期間があったとします。
- パート収入:令和7年中100万円
- 失業給付:令和7年中50万円
この場合、税金について失業給付の収入50万円は非課税とされますのでパート収入100万円のみで計算をします。
一方で、社会保険の収入はこの失業給付も含めます。
つまり、100万円+50万円=150万円と計算をします。
したがって、収入150万円となることから扶養に入れる基準130万円を超えてしまいますので扶養から外れてしまいます。
税金を計算する際、元となるのは所得ですから非課税のものは含めません。
社会保険は非課税のものも含めて計算するため収入でみないと計算できません。
遺族年金や障害年金も非課税ですがこれも社会保険では収入とみなされます。
基礎控除等の見直し
令和7年12月から税金の所得税における基礎控除が見直されます。
これまでの基礎控除はほとんどの人は一律48万円でした。
しかし、低所得者の人ほど基礎控除は大きくなり所得に応じて段階的に小さくなります。
それとともに配偶者控除を受けられる所得要件が48万円から58万円に引きあがります。
そのため、税金面では所得を正しく計算できるかというのがポイントになります。
一方で、基礎控除等の見直しは社会保険には関係がありません。
従来どおり収入がいくらかどうかで扶養に入れるかどうかを判断します。
ますます所得と収入の区別が大事になりそうだ、というのはご理解いただけるかと思います。
まとめ
今回は、税金と社会保険で取り扱いが異なる扶養の考え方を書いてみました。
税金は所得・社会保険は収入です。
では。